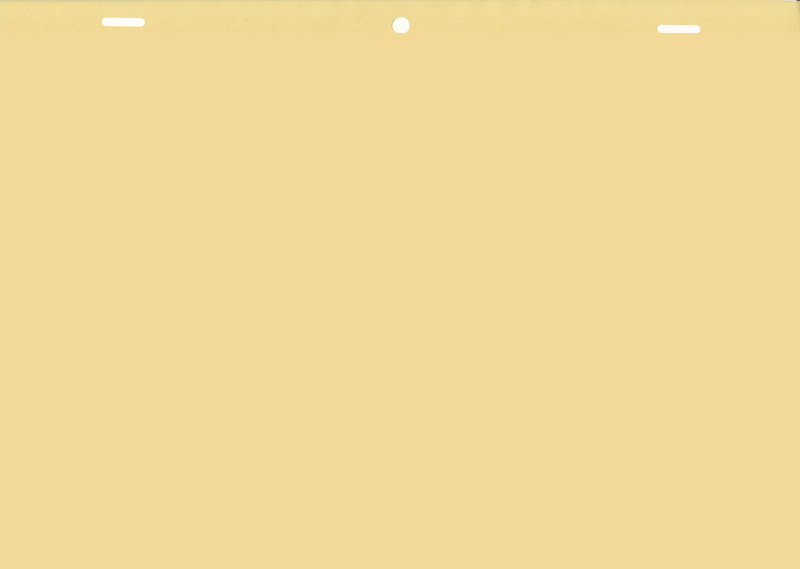絵の練習についての質問
▶ Q1,どんなに頑張っても上達しないのではないか
絵が上達しないということはありえません。努力により必ず誰もが到達することのできるラインというものがあり、それは決して低いところではないと思います。ただ、その努力の方向がどこを向いているかで、さまざまな違いは生まれてくると思います。
▶ Q2,モチベーションが下がった時の対処
描きたい時に描く、描きたくなかったら描かないと言った感じです。気分が乗らないのに無理に描いていても、仕方がないと思っていました。描かない間は、自分が描きたいと思っているモノの性質を調べたり、本を読んだり、アニメを見たりしていました。
さすがに1週間鉛筆を持たなかった時は、もう駄目かとも思いましたが、そこで辞めてしまうなら、自分の絵に対する思いなどその程度のものだと、きっぱりアニメーターになることはあきらめるつもりでいました。でも結局また描き始めました。
▶ Q3,解剖学を学んだほうがいい?
もちろん、解剖学やパースなどの知識は必要ですが、それらはどの時点で理解できた・把握できたと言えるようなものではないです。また頭の中で理解できている事も、それを絵に生かせるかというとまた別の話で、絵に生かすためには、実際にその項目を絵として描いてみて理解を深めるしかないと思います。
今は上達していないように思うかもしれませんが、何かしらの向上心をもって絵を描き続けていれば、必ず絵は上達していきます。まず絵を描くことを大前提にして、平行して知識も高めていく事が私は大切だと思います。
▶ Q4,人体のバランスを的確にとらえらるためのよい練習方法
私の場合は、各部のパーツ分けとその役割、名称を知ることでいろいろ変わっていった気がします。たとえば上腕二頭筋の両端はどの骨のどの部分に付着しているか等、暗記的な勉強も役に立ちます。
すぐ力になるわけではなく、ある時ハッとその知識と目の前にある情報との理解がつながる瞬間があって、それからは他の部位の理解も早くなりました。筋肉の大半は骨と骨をつないでいるという知識を、絵として出力する用に再度理解しなおすという感じでしょうか。
▶ Q5,参考書に描いてあるような画を一通り描けるようになれば良い?
その本に描いてある絵を一通り描くことはあまり効果的とはいえません。必要なのはその絵で説明されている内容の理解です。
料理に例えると、ただ本を見てその通りに料理を作っていても、技術全体の向上は低いですが、「料理のさしすせそ」の順番を科学的に理解すれば技術全体の向上につながります。
自分のオリジナル絵に影響を及ぼせるように意識しながら(ここが重要)本を読んでみてください。
▶ Q6,自分のレベルがどのくらいなのか知りたい
自分のレベルを知る方法ですが、一番良いのは、やはりプロに見てもらうことです。説得力もありますし。お住まいの近くにスタジオがあれば、スタジオ見学が可能かどうか聞いてみてください。OKであれば、作品を持っていけば見てもらえると思います。合わせて業界に対する疑問等あれば聞いておきましょう。
▶ Q7,クロッキーのモデルがいない
クロッキーに関してですが、一歩外に出ればいくらでもモデルはいます。だれかにモデルになってもらって10分かかるようなクロッキーもいいですが、数秒で通り過ぎてしまう人の特徴を記憶して1分かけないで描くのも面白いですよ。家に帰ってから細部を描き足してもいいと思いますし。私の場合は、外で印象的なポーズを見かけたら、記憶しておいて帰宅してからササッと描いたりもしていました。
▶ Q8,自分の頭の中で想像して描いた方がいい?
アニメーターであっても、何の資料もなく想像だけで絵を描く人は少ないと思います。キャラクター・背景・エフェクトには大抵設定がありますし、それらを上手く用いた仕事を求められます。想像で作り上げる部分は非常に少ないです。何かを参考に絵を描く作業に慣れる事も以後役に立つと思います。
▶ Q9,想像で描くことができない
大元に現実があって、それを改変することが想像だと私は思います。まず、現実そのものを見ながら描き、その一部を自分風に作り変えるように描かれてはどうでしょうか。実物を見ながら対象を上手く描けるのであれば、それと同レベルのイラストを描ける能力が備わっているということです。
▶ Q10,どの専攻を選ぶのが1番良い?
素直に自分が学びたい科目を選択されるのがよいと思います。すべての選択を、「アニメーターになるために」という囲いに当てはめて決定すると、小さくまとまってしまう気がします。アニメーターになるために必要な技術は基礎科目で学び、専攻科目では、自身の絵に関する見解や可能性を広げるために取り組まれてはいかがでしょう。結果的にそれらの経験は、「なるため」にはもちろん「なってから」も、ずっと役立てることができる強い力になると思います。
▶ Q11,どのレベルから解剖学をやっていけばいいか
私の場合ですと、まず簡単なアタリを描いてそれを元に必要な部分を盛ったり削ったりする感じです。その必要な部分を知るために、骨や筋肉単体の名称や形を学ぶことが役に立っています。通常の人物を描く場合は、パーツから考えるより人物としての塊から描くと、上手くいくように私は感じています。
アニメーターを目指す人に即戦力となる解剖学の知識は、まずデッサンの参考書などで解説されている事を理解することだと思います。それらを理解して絵に生かせたと思えた時に、まだ掘り下げたいと思ったら(または、骨や筋肉単体の絵が描きたい場合)解剖学の本で学ばれるのがよいと思います。
▶ Q12,絵を描くときはシャーペンより鉛筆の方が良いのでしょうか
私は鉛筆をおすすめします。筆圧で線の太さを変えられますし、濃淡をつける事もできます。アニメーターになると、鉛筆を使う機会も多くなるので慣れておくと便利です。ただ、シャーペンは細かいところを描きやすいので、状況に合わせて使い分けるのがいいと思います。
▶ Q13,高校三年間に何を学んでおいた方が役に立つ?
もちろん、アニメーターを目指されるなら絵の勉強ですが、それ以外にも自分のやってみたい事、やったことない事をどんどん試して欲しいです。想像だけで絵は描けません。いろいろな事を体験して絵に生かしてください。
▶ Q14,線を綺麗に書くためにはどうしたらいいのか
どの時点の線の事か分からなかったので、推測ですが。ラフの時点では多少線が荒くなっても仕方がないとは思います。クリンナップは回数を重ねるごとに必ず綺麗に描けるようになっていきます。個人によって線の引きやすい角度があります。それを見つけ出して、紙の方を回転させるようにして描いてみてください。また、鉛筆と紙を変えてみるのもいいかもしれません
▶ Q15,美術系学校卒や受賞歴があると有利?
アニメーターには、専門外からでも就職する事ができます。また美術学校を卒業しなくても、受賞歴がなくても「実力」があればそれでOKです。プロのアニメーターでも美術系の学校を出ている人はそう多くないと思います。
▶ Q16,教えられる前にれ因襲しても余計な癖がつくだけではないか
癖がつくのは誰でも経験することじゃないでしょうか。それを描き続けるうちに不自然にならない程度に調整して味に変えていけるんだと私は思っています。
就職についての質問
▶ Q17,就活の時期が分かりません
求人の時期に関してですが、業界全体がある時期にまとめて、というような感じではありません。会社ごとに変わってきますので、自分の入りたい会社を定めて、その会社の時期や方式を調べる必要があると思います。
▶ Q18,会社はどこがいいのか解りません
作品などの仕事ぶりや会社見学などでご自身が信頼できると思った場所を目指されてはどうでしょう。自分に合った会社というのは、やはり自分でしか見つけられないと思います。
そしてどこでも共通していることは、必要最低限のことは教えてくれるということです。そこから先は、自分の能力に任せるしかありません。学ぶ気持ちさえあれば、現場にいくらでも上手くなる要素は転がっているので、是非それらを利用される事をおすすめします。
▶ Q19,どの会社でも高卒では就く事すら難しい?
高校卒業から即アニメーターという道は、それほど珍しいことではありません。情報量はどう考えても会社に入ったほうが多いので、同年代が専門学校や大学に行っている間に差をつける事も可能です。
ただその場合、卒業までによくよくアニメーターの仕事を調べ、理解した上で結論を出されることをおすすめします。専門学校に行く利点の一つは、仕事内容の体験が出来ると言うことです。会社に入る前に、その部分を少しでも多く理解していないと、ギャップに苦しむ事も有り得ます。
▶ Q20,女性でも活躍できる?
女性アニメーターに関してですが、近年は特に女性の活躍がめざましいと思います。
是非OP・EDのテロップを確認してみてください。活躍している女性がどれだけ多いか、すぐわかると思います。
▶ Q21,ものすごくアニメ作品を見ているわけではありません
アニメを見た本数で、差がつくのではないかと気にされているようですが、自分はそのようなことはなく、アニメに対する姿勢によるものの方が大きいと思います。自分が感動したアニメを一本見続けて、なぜ自分にそう感じさせたのか。描き手は何を伝えようとして、どのような方法を使ったのか。それを感じ取り、自分の番が来た時にどのように応用させることができるか。
たとえ作品一本分だけでも、自分が納得できるまで掘り下げることができれば、それも大きな力になると思います。
▶ Q22,提出作品にラフは入れてもいいのか
提出作品に関してですが、なるべくラフは入れないほうがよいと思います。それはあくまで過程に生まれるもので、作品はその先にあるものだからです。ただ、クロッキーに関しては、短い時間でどこまで対象を捉えられるかという描き方なので、それはラフではなくで完成品とみなされます。
▶ Q23,手袋はしたらだめ?
自分に合った方法を見つけ出したならば、周りがなんと言おうと、「これが自分には一番やりやすいんだと」押し通してもよいと思います。大切なのは絵を描く方法ではなく、出来上がるアニメに対する貢献なので、他のスタッフと見比べても問題のないレベルに仕上げていれば、周りも何も言わなくなるはずです。
▶ Q24,通勤時間(住居)は各自の判断?
会社は交通費を支給するわけではないので、通勤距離でどうこうという事は少ないです。各自の判断に任せるといった感じだと思います。ただ、それを何かしらの言い訳にしないかどうかは見ると思います。「遠いから遅刻することもあるかもしれない」「早めに帰らないといけないので、それを考慮した仕事を振り分けてほしい」等は絶対に通りません。
▶ Q25,大学を卒業して年を重ねてしまうと不利になってしまう?
個人的な考えでは、大学卒業のための年月が就職に不利に働く印象はありません。年を重ねている理由として、社会的に筋が通っています。募集で上限年齢が25歳ぐらいに設定されているのも、大学卒業後の専門学校卒であっても採るという事だと、私は認識しています。
▶ Q26,東京に住まないと就職できない?
確かに制作会社は東京に集中していますが、最近は東京以外にも増えてきています。現在住んでいる場所の近くに、入りたいと思える会社があるかもしれませんし、一度調べてみてはどうでしょう。
動画の技術についての質問
▶ Q27,中割りのやり方が分からない
基本的な学習であれば「アニメーションの本―動く絵を描く基礎知識と作画の実際」がおすすめです。かなり古い本ですが、基本的な原・動画はもちろん絵コンテや撮影の解説等、内容は充実しています。どの会社にも一冊はあるであろうと言われている本です。ネットであれば、リンクにある「なわスタ」の「動画バカへの道」など参考になるのではないでしょうか。
▶ Q28,中割りがうまくならない
回転運動(振り向き・手の動き等)の割りは、作画の自由度が高く作画を担当した人の力量が如実に現れます。それは、アニメーターになりたいと思っていた時に想像する仕事に近いと思うのですが、線割りに慣れてしまい、前後の原画を気にしすぎると、落書きでも絶対描かないような絵になってしまったりします。
私の場合は、ササッとアタリを取ってからはキャラ表を見ながら自分の絵で描いてしまい、そこから細部を前後の原画に合わせるようにしてから直しが少なくなっていった気がします。
▶ Q29,動画作業で絵が上手くなるのでしょうか?
動画の時期はまさに、アニメーターになるための修行の時期です。ここで上手くなるというより、制作過程を知る準備として考えたほうが良いかもしれません。頑張る方向は「とにかく会社側から求められている事を達成する」でいいと思います。その過程にもしっかりと意味があるからです。画力の向上は別で進めましょう。